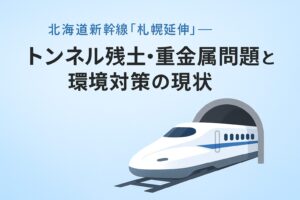金属盗難(銅線盗難の被害)|金属盗対策法改正で何が変わる
金属盗難の現状と対策|銅線盗難の被害と金属盗対策法改正ポイント
近年、金属盗難(銅線盗難・電線盗難)が全国で急増しています。太陽光発電所や通信インフラ、エアコン室外機、道路グレーチングなどが被害に遭い、 社会全体に大きな影響を与えています。本記事では、金属盗難の現状と放置した場合のリスク、さらに金属盗対策法の改正内容と効果について解説します。
金属盗難の現状|銅線盗難と電線盗難の実態
令和6年(2024年)の金属盗難認知件数は令和2年の約4倍に増加し、被害額は約140億円に達しました。 被害の中心は銅線・電線で、特に太陽光発電施設や通信設備での被害が深刻です。
銅線の盗難により発電が長期停止する事例、通信遮断による社会混乱など、金属盗難は単なる資産被害にとどまらず、経済活動や暮らしに直結するリスクとなっています。
放置すれば危険!金属盗難が招く深刻なリスク
- 社会インフラの機能不全:電力・通信・交通が停止し、地域生活や企業活動が混乱
- 経済的損失の拡大:復旧費用の増大、保険料の高騰、事業停止による二次的損害
- 治安悪化と模倣犯の増加:金属価格高騰で「割の良い犯罪」となり、模倣的な窃盗が拡大
- 再生可能エネルギー事業への打撃:太陽光発電や送電設備の盗難で脱炭素政策に悪影響
金属盗対策法の改正|改定前と改定後の違い
| 項目 | 改定前(従来) | 改定後(金属盗対策法) |
|---|---|---|
| 適用範囲 | 自治体ごとに条例がバラバラ | 全国一律で適用 |
| 規制対象 | 統一定義なし | 特定金属くず(銅+政令指定金属) |
| 業の届出 | 地域差あり | 全国で届出義務(違反は罰則あり) |
| 本人確認・記録 | 地域差や任意 | 本人確認・取引記録作成/3年間保存を義務化 |
| 盗品疑い対応 | 任意 | 警察への申告義務 |
| 行政監督 | 権限に地域差 | 公安委員会による立入検査・営業停止命令等 |
| 犯行用具 | 規制なし | 大型切断工具の隠匿携帯禁止 |
対象金属の拡張見通し
新法の対象は「銅および政令で定める金属」とされています。今後は、盗難被害が多発している アルミ・ステンレス・鉄製公共部材(グレーチング・マンホール蓋)・太陽光パネルの金属フレームなどが追加される可能性があります。
また、古物営業法施行規則の改正により、 電線・エアコン室外機・グレーチングの買取についても金額不問で本人確認が義務化され、 2025年10月1日に施行予定です。
まとめ|金属盗難対策は社会インフラ保護につながる
- 全国統一の法規制により盗品流通を効果的に抑制
- 届出・本人確認・記録保存義務で銅線盗難の被害を減少
- 警察申告義務と行政監督権限の強化で不正業者を排除
- 大型切断工具の規制で犯罪の未然防止が可能に
- 古物営業法改正との連動で入口から出口まで多層的に規制が働き、インフラ被害リスクを縮小
行政書士に相談するメリット
金属盗対策法の改正は、「盗む側」だけでなく「買い取る側・保管する側・管理する側」にも新たな義務とリスクを生じさせます。
そのため、事前に行政書士へ相談し、法令対応と実務運用を整えておくことには大きなメリットがあります。
1.自社が「規制対象になるか」を正確に判断できる
改正後は、対象が「銅および政令で定める金属」に加えて、「特定金属くずの買受業」に及びます。
しかし実務では、
- 自社が「買受業」に該当するのか
- 廃棄物か有価物かの判断はどうなるのか
- 古物営業法との関係はどう整理すべきか
といったグレーゾーンが多く存在します。行政書士に相談すれば、業態・取扱物・取引形態を踏まえて
規制対象か否かを事前に整理でき、「知らなかった」「関係ないと思っていた」という理由で
違反状態に陥るリスクを回避できます。
2.届出・社内ルール整備をワンストップで任せられる
改正対応は、届出だけで終わりません。日常業務に組み込むための運用ルール整備が不可欠です。
- 買受時の本人確認方法
- 取引記録の様式・保存方法(3年間)
- 盗品の疑いがある場合の社内対応フロー
- 職員への周知・教育
行政書士は、届出書類の作成に加えて、社内規程・マニュアル・チェックリスト等の整備まで含めて支援できるため、
「書類はあるが現場が回らない」状態を防ぎ、実効性のある体制づくりにつながります。
3.立入検査・行政指導への備えができる
改正後は、公安委員会による立入検査・報告徴収・指示・営業停止命令など、行政関与が強化されます。
事前に行政書士と準備しておくことで、
- どこを見られるのか
- 何を指摘されやすいのか
- 指摘を受けた場合、どう是正すべきか
を想定した対応が可能となり、突然の指導や業務停止などの経営リスクを最小化できます。
4.廃棄物処理法・古物営業法との“重なり”を整理できる
金属盗対策法は単独で完結する法律ではなく、以下の制度と複雑に重なって適用されます。
- 廃棄物処理法(有価物/廃棄物の判断)
- 古物営業法(本人確認義務の拡張)
- 各自治体条例
行政書士はこれらを横断的に整理し、二重規制や手続漏れの防止、運用上の整合性確保まで含めてサポートできます。
5.「守り」から「信頼を高める攻め」へつなげられる
法改正対応は単なるコストではありません。適正な法令対応は、
取引先・元請・金融機関からの信頼性向上につながります。
行政書士と連携することで、対外的に説明できる体制づくりや、
コンプライアンス重視の企業評価を獲得することも可能です。
まとめ|金属盗対策法への対応は「早期相談」が鍵
金属盗対策法の改正は、知らないうちに違反していたという事態を招きやすい内容です。
行政書士に相談することで、
- 規制対象の判断
- 手続・社内体制の整備
- 行政対応リスクの低減
- 企業としての信頼性向上
を一括して進めることができます。「まだ大丈夫」ではなく「今のうちに備える」ことが、
今回の法改正に対する最も合理的な対応と言えるでしょう。
→産業廃棄物処分業・施設許可のページはこちらへ
→産業廃棄物収集運搬業のページはこちらへ
→取組事例のご紹介のページはこちらへ
→中小企業経営者のためのM&A完全ガイド徹底解説はこちらへ
→スクラップヤード許可制へ|有価物保管も規制対象に(廃掃法改正見込み)こちらへ