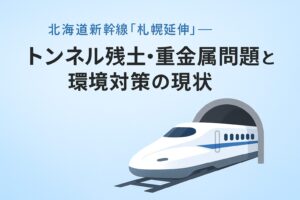ISO旅行記 留萌編 ~過疎地域の組織から学ぶ生存戦略
環境コンサル行政書士法人の若月です。
20月28日~29日、留萌に行ってきました。
今回は、ISO審査員として、建設業者様の審査に行ってまいりました。
留萌は札幌から高速を通って約2時間、およそ150㎞の距離にあります。
遠征と呼べるほどの距離にはなりますが、もしこの地域に最終処分場を作るとしたら、札幌から「近い」部類になります。

地元の老舗を訪問
今回審査で訪れたのは、留萌市に古い歴史を持つH社様。
留萌は海が近いので、港湾工事を主軸に1世紀に及ぶ歴史を築き上げてこられた地元の老舗になります。
北海道の多くの自治体は高齢化、人口減少が顕著であり、留萌市も例外ではありません。2023年にはJR留萌駅が廃止になるなど、都市機能が縮小しつつあります。
しかし、だからと言ってすべての事業が衰退しているわけではありません。
人がおり、都市として機能している限り、必要とされるのが建設業という業種です。
時流に負けない組織づくりの秘訣
一見するとさびれた街に見えますが、一概にそうではなく、どこにでも成功している人・組織はいます。地域や時流はあくまでも外部的要因で、大事なのは取り組む人が何を考えているか、ということだと思いました。
組織の代表、ご担当者様に聞いてみました。
「およそ100年、事業を続けてこられた秘訣は何ですか?」
組織様の答えは「変化」でした。
深い歴史があれば、バブルがあり、リーマンショックがあり、総理大臣暗殺があり、そして戦争がありました。
その中で、組織にも浮き沈みがあり、耐えたり、勢いづいたりしながら変化をしてきたそうです。
進化論で有名なダーウィンが残した「強者が生き残るのではなく、変化できるものが生き残るのだ」という言葉を思い出しました。
ISO審査の良いところは1日~2日ほどに時間をかけて、たっぷり事業者様と関わることができる点にあると思います。システム管理のための審査なので、ミスや粗探しのような審査になってしまいがちですが、それが審査の真の目的とは思いません。あくまで事業者のシステム上の改善点を提示するのが本旨なはずです。
その中で事業者様のお話を伺えることが一番大きな学びになります。
留萌市のH社様、ありがとうございました。