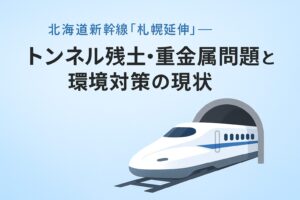行政書士が必要のない手続き?
環境コンサル行政書士法人の若月です。
祖母が運転免許を返納し、自家用車を手放すことにしたそうです。
弊所が懇意にさせていただいている自動車リサイクル業者さんに、祖母の自宅まで出張で車を引取に来ていただくことになりました。
知り合いに専門家がいるのは頼もしいですね。祖母も喜んでくれました。
さて、本題。
今回は、行政書士の上手な使い方について。
皆様は、我々、行政書士とは、一体どのような仕事をしていると思いますか。
「法的業務の代行サービス」
といったところでしょうか。
もちろん、これも間違いではありません。
しかし、それではもったいないと、個人的に思うことがあります。
もちろん、許認可申請のご依頼をいただければ、喜んでやらせていただきます。
事業者の皆様が抱える、超多忙や、人手不足の問題解決に貢献出来るのは、我々にとってもやりがいの一つとなります。
しかし、皆さんが、我々行政書士を積極的に「使い倒し」たり、
時には「使わない」選択をすることによって、自社の体制を強くしたり、コストの効果を最大限にしたり、コストカットにつなげたりすることが可能です。
なので、今回は、行政書士の上手な使い方について、解説させていただきます。
※以降の内容は筆者の個人的見解であり、すべての行政書士の総意ではありません。
上手な使い方① 行政書士に勉強させる
法の要件は難解です。
こと、廃棄物処理業においては様々な環境法令が入り組んで複雑化しています。
さらに、法律は改正を繰り返します。国家の秩序を守るためとはいえ、最新情報を取り入れ続けるのはなかなか大変な作業です。変わりゆく法律の改正に対応するために、自社に法務部を設置出来れば一番良いですが、そこまでできる組織はそう多くはないと思います。
そんな時には行政書士の出番です。
我々行政書士は「街の法律家」といわれたりします。
我々にとって法的知識は商材です。法律を読み解くことは、我々にとって「仕入」みたいなものなのです。
多くの行政書士が、条文や各種ガイドラインを読むのをルーティンとしています。
「自社を守るために法律を守るのは当然!しかし、改正情報まで、追いきれない・・・」
そんな時、行政書士を活用することをご検討ください。
上手な使い方② 行政対応の窓口をやらせる
各種許認可申請を行うときは行政の窓口を訪れ、書類を提出することになります。(郵送でも可能なもの多数)
審査をしてくれる行政担当者は基本的に優秀です。公務員試験をクリアしているわけですから、一定の偏差値は保証されているようなものです。
しかし、彼らも人間である以上、性格や個性が違います。
橇の合わない担当者さんと、喧々諤々のやり取りになり、神経をすり減らしたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
最大の問題は、知識が対等ではないという点です。
現場の知見は事業者の皆さんの方が豊富に蓄積していることが多いと思いますが、各法律を隅から隅まで読み込んでいる経営者、役員の方は少ないかと思います。
対する行政担当者はというと、法に則っていない指導はできないため、日常的に法律の規定を読み込んでいます。
法的知識でマウントを取られてしまうと、事業者は従わざるを得なくなります。
先ほども申し上げた通り、我々行政書士は、条文を読むのが仕事です。
知識においては対等です。
そのうえで、法律には「解釈」というアソビの部分が設けられています。
うまくやれば理想に近づくし、失敗すれば思わぬハンディを喰らったりします。
その落としどころを作るのは、我々行政書士の仕事です。
法律を読み解き、理想実現のために行政書士を使うことをお勧めいたします。
上手な使い方③ 人脈のハブとして活用する
弁護士、社労士、税理士など「士業」と呼ばれる方々は、士業同士のネットワークを大切にしています。
各資格において、やれることとやれないことがあり、それぞれ助け合ってクライアントの依頼を遂行するのが、サービスを提供するうえで大切だからです。
加えて、行政書士は建設業許可、廃棄物処理業許可、運送業許可など、資格における独占業務の範囲が広すぎるため、それぞれが専門分野を持っています。
同じ資格の仲間同士でも、仕事を助け合えるようにしている点で行政書士は特殊ということが出来ます。
その他、許可を取得するために処理施設のメーカー、卸売事業者、建設コンサルタント、測量士等ともネットワークを構築している場合もあります。
消費者から見れば、各士業の違いはわかりづらいと思います。
「誰に聞けばよいかわからない」といった場合に人脈のハブとして、行政書士を使ってみるのも良いかと思います。
ここまで、行政書士の使い方について解説してきました。
反対に、行政書士を使わなくてもいい(かもしれない)手続きについても、解説しておきます。
行政書士を使わなくてもいい(かもしれない)業務① 難度の低い許認可申請
行政への許可申請の手続きで、比較的難易度の低い業務を自社でやってみるというのは、筆者としてはお勧めしています。
判断基準の一つとして、「書類提出のみで許可取得が可能である」ということが挙げられます。(詳細は次のトピックに続きます)
通常、我々行政書士は請け負った申請書の控え一式を、業務完了後にお客様に提供いたします。
申請書の控えは、手続きのマニュアルとしてとても有効です。内容を少し変えれば、許可の変更、更新手続きに対応できるというケースも結構あります。
法務部門を置ける組織は限られていても、申請担当の担当者を置けるという事業者は、結構いらっしゃるのではないでしょうか。
組織内に法的業務に詳しい方がいること、マニュアルが用意されていることは、とても良いことです。
行政書士は個人事業主が多く、タイミングが悪いと、緊急事態への対応が遅れるなどのリスクを抱えています。
そんな時に、社内に頼れる人がいるのは、強い組織つくりには必要です。
それでも、わからないこと、忙しくてどうしようもない時は発生することと思います。
そんな時には、我々行政書士をお使いいただければと思います。
行政書士を使わなくてもいい(かもしれない)業務② 現地審査が発生しない
申請書の作成について、わからない個所は、行政の窓口に電話などで問い合わせると、親切に教えてくれます。
無料です。お金はかかりません。
許可の種類によっては、郵送で申請書を提出可能なものもあります。
わからないことを電話で確認しながら作成し、(可能なものは)郵送で申請書提出、ということにすれば、労力もそこまでかかりません。
正直な話、この類の手続きであれば、法律の知識が無くてもこなすことが出来ます。
こういったものは、先述した通り、自社で内製化してやる方が担当者も育つし、コストも抑えられるのでお勧めです。
しかし、手続きによっては、行政の担当者が現地(自社の事業場等)を訪れて状況をチェックする「現地確認」が発生するものもあります。
役所の担当者による現地確認は法律の要件に則り、厳格に進められます。
中には「そこまでするか」と言いたくなるほどものすごく細かいことをいわれるケースもあります。法律の要件を押さえておかないと対応は厳しいでしょう。
そういったものについては、行政書士への依頼を検討されることをお勧めします。
以上です。
いかがでしょうか。
使うときは使い倒す、必要ない時は使わない
という風に、今回の内容を我々行政書士の最大活用に役立ててください。
皆さんが、良き士業のパートナーにめぐり逢うことを祈っております。
お付き合いいただきありがとうございました。
→中小企業経営者のためのM&A完全ガイド徹底解説はこちらへ