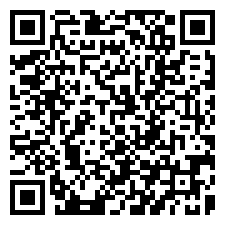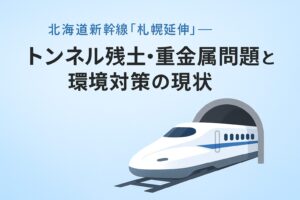適正価格とは?・のれんとは?について|中小企業経営者のためのM&A完全ガイド徹底解説2-1
第2部 パート1:M&Aの適正価格をシンプルに考える
M&Aの適正価格とは?


M&Aを成功させるために欠かせないのが適正価格の判断です。売り手にとっては「安く買いたたかれないため」、買い手にとっては「高値づかみしないため」に、双方が納得できる妥当な価格を見極めることが必要です。
M&Aの適正価格をシンプルに考える方法
中小企業においては、難しい理論や複雑な数式よりも、実務的で分かりやすい算定方法が役立ちます。代表的な考え方が、次のシンプルな式です。
適正価格 = 純資産 + M&A後3年程度の利益予測
- 純資産:会社が持つ資産(現金・土地・建物・機械など)から負債を引いた金額。会社の最低限の価値を表します。
- M&A後3年程度の利益予測:今の顧客や事業基盤を前提に、M&A後3年程度でどのくらい利益を出せるかを見積もります。
例:純資産が5,000万円、M&A後3年程度の利益見込みが3,000万円の場合、
5,000万円 + 3,000万円 = 8,000万円 が適正価格の目安になります。
4. この方法のメリット
- 難しい数式を使わないので、経営者同士が納得しやすい
- 過去の実績と将来の稼ぐ力をバランスよく反映できる
- M&A後3年程度という短めの予測なので、根拠が比較的立てやすい
5. 注意点
ただし、この方法は「シンプルで分かりやすい」反面、以下の点には注意が必要です。
- 将来の利益予測は、売上減少や競合環境の変化を見込んで慎重に立てる
- 特殊な許可やブランド、独自技術など「見えない価値」がある場合は、別途加味する
- 簿外債務や将来の投資リスクがある場合は、その分を差し引く
✅ この「純資産+M&A後3年程度の利益」で考える方法は、M&Aの専門家が使う難解な手法よりも、経営者同士が話し合いで合意しやすく、中小企業の現場にとてもマッチしています。
のれんとは?
実際のM&Aでは、買収価格が純資産を上回るケースが多くあります。この差額をのれん(Goodwill)と呼びます。のれんには、次のような「目に見えない価値」が含まれます。
- 長年の顧客との信頼関係
- 社員や組織の力
- ブランドや知名度
- 独自の技術やノウハウ
- M&Aによるシナジー効果への期待
のれんを計上することで、「なぜ純資産以上の金額を払ったのか」を会計上で整理できます。ただし、期待が外れれば減損損失として処理されるリスクもあるため、注意が必要です。
なぜ「のれん」という考え方が必要なのか?
- 目に見えない価値を数値化できる:決算書に載らない強みを反映できる。
- 買収価格の説明ができる:純資産との差額を「ブランド力やシナジー」として示せる。
- 経営の透明性を高める:投資判断の背景を株主や関係者に説明しやすくなる。
- リスク管理の仕組み:定期的な減損チェックで投資判断の妥当性を検証できる。
「のれん」と「M&A後3年程度の利益」の違い
- M&A後3年程度の利益:将来の稼ぐ力を予測した「期待」。価格を考えるときの参考材料。
- のれん:実際に支払った買収価格と純資産との差額。会計上の「無形資産」として処理される。
例:純資産5,000万円の会社を「M&A後3年程度で3,000万円の利益が見込める」と考えて8,000万円で買収した場合、差額の3,000万円がのれんとなります。
M&A後3年程度の利益 = 期待
のれん = 実際に払った証拠
まとめ:シンプルな評価と透明な会計
M&Aの価格を考える際は、難解な理論にとらわれる必要はありません。
「純資産+M&A後3年程度の利益」でシンプルに評価することが、経営者にとって最も分かりやすく実務的です。さらに「のれん」という仕組みを理解することで、純資産以上の価値をどう説明するのか、そしてどんなリスクがあるのかを明確にできます。
M&Aサポートのページははこちら
環境コンサル行政書士法人へのお問合せはこちらへ