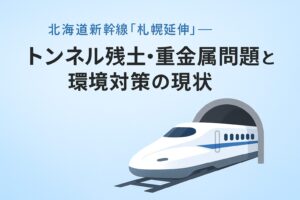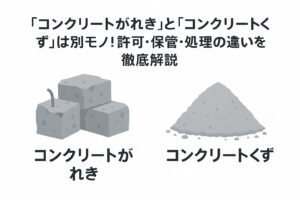【2025年施行】再資源化事業等高度化法とは | 産業廃棄物処理業許可申請
廃棄物処理法との違い・改正ポイント・企業への影響を徹底解説
2025年11月21日に全面施行される「再資源化事業等高度化法(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)」。制定背景、法内容、改正前後の違い、企業・自治体への影響、海外動向を、最新データと日付を示して体系的に解説します。
1.再資源化事業等高度化法とは何か
1-1 正式名称と施行スケジュール
本法の正式名称は「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(令和6年法律第41号)です。
略称として「再資源化事業等高度化法」または「高度化法」が使われます(※再資源化事業を高度化し、国内の資源循環を強化するための基本法)。
- 閣議決定:2024年3月15日
- 成立・公布:2024年5月29日
- 全面施行:2025年11月21日(予定)
1-2 法律の目的
本法の目的は、次の三点に要約されます。
- 高度かつ効率的な再資源化の実施
- 再資源化工程の生産性向上と温室効果ガス削減
- 高品質かつ安定した再生資源の供給体制の構築
単なる「リサイクル量の増加」ではなく、
“高品質な再生材の安定供給と脱炭素化の両立” を目指す点が特徴です。
2.制定の背景:なぜ今「高度化法」なのか
2-1 日本の資源循環の現状と課題(最新データ)
以下は日本の最新統計(2022〜2024年度)です。
- 産業廃棄物排出量:3億7,407万トン(2022年度)
- 一般廃棄物排出量:4,034万トン(2022年度)
- 一般廃棄物1人1日排出量:880g
- 廃棄物部門の温室効果ガス排出の約8割が焼却由来
また、世界的な比較では、
- 世界のプラスチック生産のうち再生材比率は9.5%(2022年)
- 日本のPETボトルリサイクル率は94%と高水準だが、1人当たりプラスチック消費量は世界上位(約129kg/年)
つまり、
「量として集められている一方で、高付加価値な再生材供給が追いついていない」
ことが制度改正の前提となっています。
2-2 政策体系の中での位置づけ(GX政策との連動)
2025年には、以下の改正も行われました。
- 改正資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)
(※略称:資源有効利用促進法、製品のリサイクル設計・再生材利用を推進する法律)
内容は、
- 再生資源利用の義務化
- 環境配慮設計の認定制度
- GXに資する再資源化等の促進
など、“製造側(動脈産業)に再生材の利用を求める仕組み”です。
これに対し、再資源化事業等高度化法は
“廃棄物処理・リサイクル側(静脈産業)を高度化する仕組み”。
両者はセットで資源循環を強化する「両輪」として位置づけられます。
3.再資源化事業等高度化法の主な内容
3-1 基本方針の策定と役割分担
本法では、環境大臣が「高度化基本方針」を策定し、国・自治体・事業者の役割を明確化します。
- 国:基本方針・判断基準の策定、認定制度の運用
- 自治体:基本方針に沿った地域施策の実施
- 事業者:再資源化の取組み・情報開示の推進
3-2 特定産業廃棄物処理業者の「報告・公表制度」
一定規模の処分量を持つ事業者は、再資源化の実施状況を国に報告し、その内容が公表される制度が導入されました。
業界全体の透明性向上とベンチマーク(横比較)が進む点が重要です。
3-3 「三つの認定制度」の創設
高度化法の中核は、次の三類型の認定制度です。
(1)高度再資源化事業
広域的な分別回収・再資源化スキームを構築する事業。
(例:太陽光パネル、風力ブレード、廃食油→SAFなど)
(2)高度分離・回収事業
高難度の分離技術を用いて、再生材の質を高める事業。
(3)再資源化工程高度化事業
既存処理施設の高度化(高効率設備導入・脱炭素設備導入など)を行う事業。
いずれの類型も、国が認定し、事業計画の確実性と社会的妥当性が担保される構造です。
3-4 廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の特例
認定事業者には、廃棄物処理法上の許可・施設設置許可の一部が簡素化される特例があります。
また、類型①・②に該当し、環境大臣が定める設備を導入した場合、
取得価額の35%を特別償却可能(税制特例)となりました。
4.「改正前」と「改正後」で何が変わるのか
4-1 高度化法の制定による変化
従来(~2024年)
- リサイクル関連制度は各法で個別に管理
- 広域連携・高効率設備導入の許認可が個別自治体ごとで煩雑
- 再資源化の実績情報は十分に公開されていなかった
高度化法施行後(2025年11月~)
- “高度な再資源化”の判断基準が明確化
- 認定事業に限り、許可手続きが合理化
- 処理業者の再資源化実績が公開され、競争・改善が加速
4-2 資源有効利用促進法(動脈側)の改正点
- 再生資源利用の義務化(製造事業者に計画・報告を義務付け)
- 環境配慮設計(分解しやすさ・長寿命設計など)の認定制度創設
- GXに必要な原材料の再資源化促進
- シェアリング・リユース等のCE(Circular Economy)コマースを制度化
製造側に「再生材を使う」義務が生じるため、
高度化法に基づく“供給側の高度化”が必須となる構図です。
5.制度のメリット
5-1 産業廃棄物処分業者・リサイクル事業者
- 広域型・新規事業への参入が容易
- 設備投資の税制支援(特別償却)
- 国の認定により信用力が向上
5-2 排出事業者(製造業・建設業等)
- 再生材利用義務への対応が円滑
- 安定供給・トレーサビリティの確保
- スコープ3排出削減の推進に貢献
5-3 自治体・社会
- 最終処分量削減
- 焼却依存の抑制と脱炭素化
- 地域循環共生圏の形成促進
6.海外動向
6-1 EUのサーキュラーエコノミー政策
EUは、2030年までに素材循環利用率を約2倍(23%台)にする目標を掲げています。使い捨てプラ包装規制やEPR(拡大生産者責任)の拡張など、規制強化が続いています。
6-2 世界的なプラスチック問題
- 世界の再生材比率は9.5%(2022年)
- 埋立40%・リサイクル27.9%という状況が続く
6-3 日本の位置づけ
- PETリサイクル率は世界最高水準
- 一方でプラ消費量は世界上位
高度化法と改正資源法は、
“高品質な再生材を国内で循環させる体制への移行”を促す制度設計と言えます。
7.まとめ
- 高度化法=静脈側(廃棄物・リサイクル)の高度化を図る新法
- 資源有効利用促進法=動脈側(製造)の再生材利用を義務化する既存法の改正
- 両法はセットで、日本の資源循環を「量から質へ」転換する法体系
2025年以降は、
高度な再資源化の実装、事業者間連携、設備投資の最適化が企業競争力に直結する時代へ移行します。
→「ついに施行された再資源化高度化法|産廃処理の常識が変わる“認定制度”の全貌」はこちらへ